令和7年3月4日、国土交通省はマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案が閣議決定したことを伝えました。背景には、マンションの総数が700万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の「二つの老い」が進行し、外壁の剝落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化していることを挙げています。このため、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生の円滑化等を図ることの必要性から、法改正に至ったと公表しています。
出典:国土交通省HP
法改正案の柱は3つあり、
1.マンションの管理の円滑化等
2.マンションの再生の円滑化等
3.地方公共団体の取組の充実
となっています。
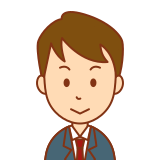
今、マンションに何が起きているのでしょう。
どうして法改正に至ったのか、法改正案の3つの項目について見ていきます。
マンションの管理の円滑化が必要な理由
築40年以上のマンションでは、管理組合の機能不全が深刻化し、適切な修繕が行われないケースが増えています。例えば、修繕積立金が不足し、必要な修繕工事が実施できず、外壁の剥落や給排水管の劣化による漏水が頻発するマンションが報告されています。管理組合の役員のなり手不足により、意思決定が滞り、管理不全に陥るケースもあります。
・修繕積立金の不足により計画的な修繕が困難な場合があること
・管理組合の機能不全による意思決定の遅れ
・高齢化に伴う役員のなり手不足
・管理業者との利益相反による不透明な契約
法改正案(国土交通省HPより)
①新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入。
②マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化。
③修繕等の決議は、集会出席者の多数決によることを可能に。
④管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設。
マンションの再生の円滑化が必要な理由
老朽化したマンションの建替えが進まない理由の一つに、区分所有者の合意形成の困難さがあります。例えば、築50年を超えるマンションでは、耐震性が不足しているにもかかわらず、建替え決議に必要な4/5の賛成を得られず、再生が進まないケースが多く報告されています。建替えに必要な資金負担が大きく、住民の経済的負担が障壁となることもあります。
・建替え決議に必要な多数決のハードルが高い
・耐震性不足のマンションでも再生が進まない
・建替え資金の負担が大きく住民の合意形成が困難
・隣接地や底地の所有権整理が進まず再開発が停滞する
法改正案
①建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議によることを可能とするとともに、これらの決議に対応した事業手続等を整備。
②隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に。
③耐震性不足等で建替え等をする場合における特定行政庁の許可による高さ制限の特例を創設。
地方公共団体の取組の充実
地方公共団体が関与できる仕組みが不十分なため、危険な状態のマンションへの対応が遅れるケースが報告されています。例えば、外壁の剥落や鉄筋の露出が進んでいるにもかかわらず、管理組合が適切な対応を取れず、住民や通行人に危険が及ぶ事例が発生しています。区分所有者の合意形成が難しく、建替えや修繕が進まないマンションが増えています。
・危険なマンションへの対応遅れ
・地方公共団体が関与できる法的枠組みが不十分
・区分所有者の合意形成が困難で再生が進まない
・専門家の支援を受ける仕組みが不足
法改正案
①外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置。
②区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設。
建物と区分所有者の二つの老い
マンションの「二つの老い」は、単なる建物の老朽化だけではなく、所有者の高齢化とともに、管理・再生における意思決定の停滞をもたらしています。
修繕が進まず、建替えの合意形成が困難なまま、都市の中に「動かない建物」が増えていく現状に対し、今回の法改正は、管理計画の義務化や再生決議の緩和、地方自治体の関与強化など、実効性のある対策を講じています。
マンションは「所有する資産」から「安全な居住空間」へと意識を転換することが求められています。
今後、この法律がどのように実施され、マンションの未来を形作っていくのか、住民一人ひとりがその動向を注視する必要があるでしょう。


