2020年10月8日 NHK NEWSWEB
菅内閣が行政手続きでの押印廃止を進める中、はんこ文化を守ることを目指す自民党の議員連盟は、高齢者やデジタル化に対応できない人たちにも配慮し、国民の理解を得ながら改革に取り組むよう求める要請書をまとめ、政府に申し入れました。
はんこ文化を守ることを目指す自民党の議員連盟は8日、総会を開き、菅内閣がすべての行政手続きで原則押印を廃止する方針を示していることを受けて、政府への要請書をまとめました。
この中では「デジタル化は時代の流れであり全面的に支持するが、あまりにも拙速で行き過ぎた『脱ハンコ化』によって、押印に対する国民の信頼が大きく揺らいでいる。長年貢献してきた業界の人々に多大な被害が生じている」と指摘しています。
また、口座からの不正な引き出しなどが相次いでいることを踏まえ、「はんこは本人確認などのための極めて有効な手段で、廃止は現時点ではありえない」と強調しています。
そのうえで「高齢者をはじめデジタル化に十分対応できない人にも『弱者切り捨てではないか』と動揺が広がっている」として、国民の理解を得ながら改革に取り組むよう求めています。
このあと議員連盟のメンバーは総理大臣官邸を訪れて、加藤官房長官に要請書を手渡しました。
議員連盟の会長代行を務める城内元外務副大臣は、記者団に対し「デジタル化は目的ではなくて手段だ。『はんこを廃止すればすべてがうまくいく』と、はんこを悪者にすることはやめてもらいたい」と述べました。
デジタル化の足枷となる「はんこ」
加藤官房長官は記者会見で、
という団体の懸念に対し、
「デジタル化とはんこの文化はぶつかっている訳ではなく、不要な押印等の廃止を含め、書面や対面が必要な手続きについて抜本的な見直しを進めていく」
と述べています。
日本の企業において、今ではメール等による社内周知が行われていますが、それ以前は「回覧板」による社内周知が一般的でした。
回覧を見たら押印し、印のない人の席に回覧を置く。
押印は「見たよ」と示す為のものでした。
当初、電子メールは相手が「見たか」「見なかったか」送信者は把握することができませんでした。
ラインでは「既読」表示があり、送信者は相手が見たかどうかリアルタイムで把握できます。
「既読」は回覧板で言う押印と同じような機能と言えます。
メールに代わりラインが普及した理由の一つかと思われます。
話は変わりますが、紙文化においての「はんこ」は、法人にしろ個人にしろ正規な書面であることの「証」でもあります。
手彫りの「はんこ」であれば、たとえ偽造しても全く同じものを作るのは困難でしょう。
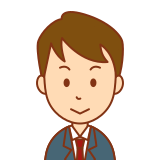
当初、「はんこ」は唯一無二の存在でした。
「はんこ」が機械で掘られるようになり、一般的な苗字であれば100円ショップでも手に入る時代です。
唯一無二の存在でなくなった時点で、「はんこ」の価値は無くなったように思われます。
三文判を押す行為は、その慣習の何物でもありません。
デジタル化において、書面上の印章は「飾り」に過ぎないよう思われます。
印章をスキャンすれば偽造も簡単に行えることでしょう。
大切なのは、発行元や本人確認かと思われます。
「はんこ」がこの役割を担ってきましたが、日本人は「はんこ」の効力を過信してきたのかも知れません。
-1.jpg)

