江藤拓農林水産大臣が、3月14日の閣議後会見で、アメリカのホワイトハウス報道官レビット氏について「大変若い報道官でいらっしゃって、お美しい方だなと思いました」と発言しました。このコメントが「ルッキズム」(外見で人を評価すること)を助長する可能性があるとして議論を呼んでいます。
レビット氏は、記者会見で日本のコメに対する高関税(700%)を批判しており、江藤大臣の発言はその受け止めを問われた際の発言です。
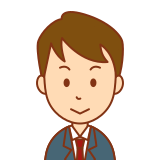
なぜ、中高年はこのような失言をしてしまうのでしょう?
SNSの普及で消えた「お世辞」と「社交辞令」
かつて日本の社会においては、「お世辞」や「社交辞令」は円滑な人間関係を築くための潤滑油として機能していました。
例えば、「この服お似合いですね」や「また今度ご飯でも行きましょう」という言葉は、相手を喜ばせたり場を和ませたりするために交わされるものです。
これらは、必ずしも本心から発せられるものではなくても、礼儀や配慮の一環として尊重されてきました。
しかし、SNSが日常のコミュニケーションの主戦場になるにつれ、この「お世辞」や「社交辞令」の役割が機能不全となっています。
SNS上では、文字通りの解釈が主流となり、微妙なニュアンスや間接的な表現が誤解されるリスクがあります。
そのため、「お世辞」や「社交辞令」といった暗黙の了解に頼るコミュニケーションが使われなくなっています。
加えて、SNSでは「本音」が称賛され、率直な意見が重視される風潮が根付いています。
「忖度しない」「ありのままの自分を出す」といった姿勢が共感を呼ぶ一方で、かつては日常の潤滑油として有効だった「お世辞」や「社交辞令」は、むしろ「嘘偽り」や「おべっか」として敬遠されています。
中高年は「お世辞」と「社交辞令」は禁止です!
お世辞や社交辞令の習慣は、時代と共にその役割を終えています。
特に外見を褒めるお世辞は、ルッキズムやセクハラ等のハラスメントを助長する原因となります。
相手を気遣うつもりで言った言葉が、不快感や誤解を生む可能性があるのです。
また、社交辞令として使われる「また今度」という言葉は、相手に期待を与える一方で、実現しないことが多く信頼を損なうこともあります。
現代社会では、コミュニケーションの透明性と誠実さが何よりも重視されています。
本音で語り合うことが、信頼関係を築く土台となるのです。
お世辞や社交辞令を捨て、相手の内面や具体的な行動を尊重した言葉を選ぶことで、より健全で深い関係性を築くことができるでしょう。
古い習慣に縛られるのではなく、新しいコミュニケーションの形を考えるべきです。


