給料から天引きの社会保険料等とは
労働基準法では、賃金の「全額払いの原則」により給料からの天引きは認められていません。
ただし、法令で定められた税金、社会保険料等については天引きが認められています。
会社に勤めている時は、天引きにより支払われていましたが、退職後の無職期間は自身で支払う必要があります。
自身に届いた納付(納税)通知書
令和4年12月31日付で退職した自身にも納付(納税)通知書が届きました。
国民健康保険料 64,650円(令和5年3月分迄)
国民年金保険料 49,770円(令和5年3月分迄)
住民税(市・道民税) 29,600円(令和5年5月分迄)
合計 144,020円
「国民健康保険料」と「住民税」は所得や市区町村により異なります。
算定の根拠となる所得は、どちらも174万円/年です。
当然ながら所得が多ければ、どちらも負担金額は増えます。
無職・無収入の身にとっては大きな出費であり、この出費は序章に過ぎません。
尚、「国民年金保険料」は全国一律的な(早割り等ある)保険料です。
退職後に留意すべきこと
「国民健康保険料」と「住民税」は、上記の場合において令和3年1月~12月の所得を算定根拠にしています。
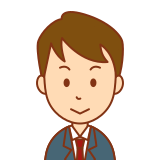
つまり前年所得が算定根拠となります。
今回、その支払いを終えたに過ぎません。前節で序章と言ったのはそういう意味です。
自身も令和4年1月~12月の所得に応じた額の保険料や税金を、今後納めることになります。
無職・無収入には厳しい期間と言えます。
その支払いが済み、令和5年1月~12月が算定根拠となれば、自身の場合において世帯所得が0となり「国民健康保険料」と「住民税」は格安なものとなります。
(格安の金額を知りたい方は、お住まいの市区町村に問い合わせすれば、その金額を知ることができます。)
退職を経験された方は、誰もが承知していることと思われますが、経験されていない方にとっては「無職・無収入でも、この金額を支払うの?」と制度に疑問をもつことでしょう。
特に大企業に長年勤められ、60歳で定年し嘱託社員として働く方の中には、前年所得が高く嘱託社員の給料が安いため、およそ1年間働いてもタダ働き同然との話も聞きます。
無職・無収入でなくても金銭的に厳しい期間は存在するようです。


