老後の資産運用は、限られた資産をどのように運用し、安心した生活を築いていくかが、多くの人にとって大きな課題です。
しかし、その選択肢の中には注意すべきものもあります。
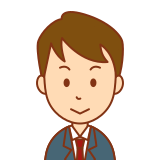
それは毎月分配型の投資信託です。
毎月分配型の投資信託は、定期的な収益が見込めるように思えますが、元本が減少しやすい構造を持つため、長期的な資産形成には向きません。
そのような現状下で、新たな資産運用制度「プラチナNISA」が構想されています。
この制度がなぜ「高齢者向け」なのでしょう?なぜ若者に勧めないのでしょう?
毎月、お小遣い感覚で分配金を受け取れ、家計の足しにもなる資産運用と言えるかもしれません。
それなら高齢者に限定する必要はありません。
若者に毎月分配型を勧めないのは、元本の減少リスクが高いからです。
元本の減少リスクとは
毎月分配型の投資信託で頻繁に分配金を支払うことにより、投資元本が徐々に削られてしまう可能性があることを指します。
実際の運用益以上の分配
毎月分配型のファンドは、投資収益を元に分配金を支払います。
しかし、もし運用による利益が十分でない場合でも、過去の分配水準を維持するために元本を削って支払うことがあります。
この場合、資産そのものが目減りし、長期的な運用が難しくなります。
元本払戻金(特別分配金)の影響
分配金には、運用益から支払われる「普通分配金」と、元本を取り崩して支払われる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
特別分配金が続くと、投資元本が減少し、最終的に資産が大きく目減りすることになります。
見かけ上、毎月分配されているように感じますが、実際には自分のお金を取り崩しているだけのケースもあるため注意が必要です。
運用効率の低下
分配金を支払うことでファンドの資産が減り、複利運用の効果を十分に活かせないこともリスクの一つです。
例えば、分配をせずに運用を続ける投資信託では、利益が再投資されて雪だるま式に増えていきますが、毎月分配型では利益の多くを定期的に支払うため、長期的な資産形成には向きません。
投資信託の基準価額の低下
分配金を支払うたびに投資信託の資産が減るため、基準価額(1口あたりの価格)が下がりやすくなります。
長期的に見ると、安定的な資産運用が難しくなり、結果的に投資の価値が低下します。
一度低下した基準価格は戻りにくい傾向にあり、当初の分配金の額も減っていくのが現状です。
高齢者における毎月分配型のメリット
人生の最終章を迎えたとき、資産を最大限に活用することが大切です。
毎月分配型の投資信託は、長期的な資産形成には向かないかもしれませんが、元本の減少を気にせず 今の生活を豊かにする手段 としては有効です。
将来のために資産を残すのではなく、毎月の分配金を楽しみながら使うことで、ゆとりある暮らしを実現できます。
天国にお金を持っていくことはできません。
だからこそ、今を大切にし、資産を人生の充実に活かす選択肢として毎月分配型は有効かもしれません。
ただし、
「資産を大切な家族やお孫さんに残したい」と考える場合には、毎月分配型の投資信託は慎重に検討する必要があります。
定期的な分配金が支払われる一方で、元本が削られていく可能性があり、長期的には資産が目減りしやすくなります。
そのため、資産を次の世代に継承することを重視するなら、より持続的な運用を考えるほうが適切かもしれません。
最後に、全てにおいてリスクと書いていますが、元本が目減りする商品と割り切った方がいいでしょう。
.png)

